| パネリスト |
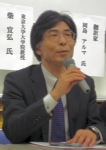 |
 |
 |
 |
柴宜弘氏
(東京大学大学院総合文化研究科教授) |
河原仁氏
(外務省中・東欧課地域調整官) |
岡島アルマ氏
(旧ユーゴスラビア出身/語学講師) |
田淵大輔氏
(文教ボランティアズ代表/文教大学国際学部国際関係学科3年) |
内容:
最初に各パネリストによる自己紹介。
次に「共生」についてのディスカッション。
田淵氏が訪れたボスニアのユースセンターでは受け入れ対象が単一の民族に統一されている現状に触れ、共生は難しいのではとの意見が出された。
これに対し岡島氏は、「私たちは紛争の前までは仲良く暮らしていた」と強調。
河原氏は、チトーの時代も「兄弟愛と統一」を演説の度繰り返し国民に訴えるなど、共産主義や人民軍の縛りをつけなければならなかったほど共生は難しかったと発言した。
柴氏は75〜77年に自身が旧ユーゴにいた時は民族的な対立をあまり感じられなかったことに触れ、ユーゴ解体については宗教紛争や民族紛争だけでなく、社会主義崩壊の過程の中での出来事であるという視点を失ってはいけないと指摘した。民族感情を煽る政治家がどこにでもいて、それが民族紛争に転化していったと説明、歴史教科書の問題にも触れた。90年代から自己中心的な教科書が改定されていき、スロヴェニア、クロアチアでは複数ある教科書の中から使用するものを選択できるが、ボスニア、セルビアでは一種類の教科書しかなく政治と教育との関係が密接になっている。そのような中、オルタナティブな形で共通の歴史資料集をバルカン12カ国で作る動きが出ており、実際に昨年度には英語で出版されたことを紹介した。
最後に田淵氏がボスニアの強制収容所で暴行などの被害にあったムスリム人に「私の骨を砕いた犯罪に対しての憎しみはあるが、セルビア人という民族への憎しみは抱いたことがない」と言われたことを話し、民族自体を憎むのではなく、彼らが犯した行為そのものを怒りの対象とみなしている人が増えていることで共生への希望が見えてくるのではと発言した。
また、「日本にいる私たちにできること」についてのディスカッションも行われた。
河原氏が04年、西バルカン平和定着・経済閣僚会合を日本とEUが共催したことに触れた。そして、政府レベルに限らず、NGOなどあらゆるレベルで関わっていく必要があると発言。
岡島氏は、スポーツや音楽を通しての文化交流がもっとも簡単であると述べた。そして日本も地球の一部であり世界は一つなのだから、一人ひとりが責任をもってこの世界をつくり上げていくべきだと締めくくった。
最後に、質疑応答を行いパネルディスカッションは幕を閉じた。
![]()
